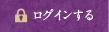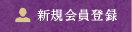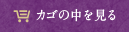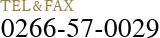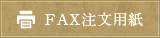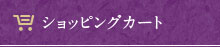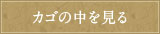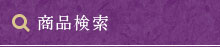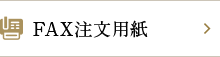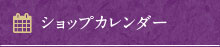剣道防具を選ぶ時の防具について知っておきたいことを学んでみましょう。
防具の種類は大きく分けて・ミシン刺しと手差しに分けられます。
それでは・ミシン刺しにはどんな種類があるのでしょうか?
1.大きく刺した10mm刺し、その次に細かい8ミリ・刺次に細かい6mm刺・5mm刺し・4mm刺・3mm刺と言うように沢山の刺し方があります。
勿論細かい刺し方に防具の値段は高くなっていきます。
2、次にその刺し方の違いもあります。
例えば「面」に関して言えば、布団の刺し方が具の目刺と斜め刺し、棒刺しの三種類に最近では、10mm十字刺しとか8mm十字刺しや6mm十字刺しなどの刺し方が増えてきましたね。
それに合わせて「小手(甲手)」垂なども刺しが面と同様の刺しになりセットとなります。
胴の胸の模様は、燭光とも言います。代表的な物には鬼雲に詰刺し(紺色・エンジ・鉄紺など)、本雲詰刺し、東京S字刺し、総刺波千鳥、亀甲模様などなど、今人気の「鬼滅の刃」でお馴染みの「市松模様」なども古くから高級防具に用いられる燭光として有名です。様々な胸の模様が沢山あります。
また、オーダーメイドで自分だけのオリジナルの燭光を作ることもできますね。
胴台の種類について説明しますと裏側がつるつるしたヤマト胴台ですが一般的に幼年用防具や少年用防具、入門用防具や初心者用防具に用いられている代表的な胴台と言えるでしょう。価格を抑えて入門者が揃えやすいか価格を安くお求め易く設定できる素材でもあります。
次にはよく耳にするかと思いますが、50本型樹脂胴(50本型強化樹脂胴とも言います)です。胴台の裏側が「竹胴」のような模様になっているのが特徴です。先程のヤマト胴台に比べて少し厚く胴を打たれてもお腹に響かないしっかりした長持ちのする素材です。最近では手刺しの防具にもこの50本型樹脂胴がセットとして組み込まれることが多くなっています。
セット防具としては、織刺しの防具でも少し高めの価格の防具やクラリーノ仕様の防具にも用いられています。
そのほかには軽くて丈夫なフアイバー胴も従来から人気のある胴台になっています。
では胴台の模様も沢山見かけますが一体どんな模様や色があるのでしょうか?
「色付きの胴」又は「代わり塗り胴」などとも呼ばれています。溜塗や青貝や高価な胴としては「サメ胴」など沢山の模様や色があります。
色付き・代わり塗り胴は試合用としてチーム胴など団体戦でチームの一体感を出すため統一した胴の模様で揃えるチームが中学校や高校などチームで校章など胴台にプリントして揃えることがあります。
高級な防具には、手刺しの2分刺しや1分5厘刺し、1分刺しなど刺しの細かさにより価格も違ってきますが、胴台は43本立て、50本立て、60本立て72本立ての竹胴の上に「にかわ」を塗りその上に「漆」を何回も塗り重ねていく高級な胴があります。
胴台の模様には先程の模様と同じような様々なものがありますが「漆」を塗って磨き上げていますので自然とその色も素晴らしい光沢を映し出しています。
小手は甲手ともいわれ防具の中でも一番需要が多く成長とともに手に合わせてサイズを変えたりいたみも早いため手の内の張替えや小さな穴などは革を当てるなどの簡易的な修理をするようになります。ご自分の手に合った小手を探すのに苦労もする部品です。ですので私も甲手の種類は常に形やサイズの違った物を用意するよう心がけています。
剣道防具の中で一番「オーダーメイド」するのも多いですね。
手の形は人それぞれ違いがあります、また同一人でも右手と左手では手の形やサイズが異なります。ですので手の一部として小手をはめている感覚がないくらいの小手が一番「技」を出したり、手の内を作っていく上には疎かにできないところでもあります。
指の長さや手の甲の厚いさや掌の大きさなど既存の小手ではぴったりフィットする小手を探すのは難しい方もおられますね。オーダーメイドの小手と言っても価格を抑えた安い小手から鹿革を使用した高級な小手や手刺しの高級な小手までその値段はさまざまです。
また中には、稽古用にと安くて軽く軽量な仕立ての替え小手などを用意する方もおられますし子供さんでは手の成長も年々違いますので価格を抑えた激安の小手や特価小手で揃えることも多いようですね。
垂はどんな種類とサイズがあるのでしょうか?
垂の種類からですが、面や小手と同じように刺す大きさは様々です。面や小手の刺し方に合わせてセットとなります。
仕様は、8mm・6mm・5mm刺しでフチクラリーノ仕立て角革付きまたは袋とじ、5mm刺し・3mm刺などで総クラリーノ刺し、ジャバラは細いジャバラと太いジャバラがありますがお値段が安い防具はジャバラが細くまた、本数も少なく3本・4本になります。
お値段が高く見栄えの良い垂ですと、5mm刺しや3mm刺・手刺し防具になりますとジャバラも太く本数も5本・6本・7本などと多くなり見栄えも良く高級感も増してきます。
またお安い防具はジャバラの色が紺色に対して高級防具になりますと紫色・茶色・鉄紺などのカラーがありまた、オーダーで色の指定も可能になる防具もあります。
高い防具になりますと、斜め刺しや額刺しなど刺し方にも変化があり使い勝手や見栄えも良くなってまいります。
人気の防具はどんなのがあるのでしょうか?
一つは、軽く仕立ててある軽量防具です。
女性の剣士も多いこともあり「軽い」と言う事は稽古がしやすいとか動きやすいという安心感が持て防具を選ぶ基準として重要な条件になってくると思います。
最近は素材も非常によくなってきたことから軽量防具でも丈夫でしっかりした仕上げになっていますので長く使用でき安心ですね!!
特に面金はジュラルミンが主流で大変軽くまた錆ない優れものもので幼年や少年用防具、入門者や初心者を含め長く剣道をされている方にも人気です!!
次に防具を選ぶ条件としましては「清潔な防具」に人気がありますね!
「消臭対策をしてある防具」です!!
消臭対策は汗などの悪臭を糸が素早くスピーデイーに消臭、吸収したニオイを科学的に取り除く仕様であったり、汗を吸汗、拡散、速乾、抗菌、防臭対策をしてありニオイに対して安心感を持てる仕様の防具に人気があります。
グンゼのコアーミシン糸を使用してその効果がが得られるような対策を施してある防具などが販売されています。
その他に何と言っても誰もが求めている「洗える防具」です。
ご使用者本人が「洗える」防具です!!
特に「甲手・小手」です。
防具の中でも面と甲手・小手は直接肌に触れ汗が直接染みる為「ニゴイ」がひどく剣士の悩みの一番になっています。
洗える小手はぬるま湯に漬けて湯の汚れがなくなるまで3~4回ほど変えて洗えば嫌なにおいが取れて綺麗になります。あとはしっかり乾かすだけです。
面はご自分で洗うのは大変ですので、「内輪の取り換えのできる」面が便利ですね!!
勿論「垂」も洗えるタイプが出ています。
面・小手・垂共素材は「ジャージ生地」の防具になります。
軽量で色落ちせず色も紺生地と変わりありません。
従来の「藍染生地」の防具をご使用の方はご自分で洗うのは危険ですのでそういった方はお持ちいただけば「クリーニング」いたしますので是非ご検討ください。
当店のクリーニングは「科学洗剤」を使用していませんので防具にも優しく化学洗剤の嫌な臭いも付きませんので安心です!!
防具クリーニングのお問い合わせはこちらまで:0266-57-0029
防具は一体どのくらい使えるの?
特価防具や激安防具などで安売り用に作った防具は傷みが早いかもしれませんが、通常は10年とか20年などかなり持ちます。通常1週間に3~4回の稽古を想定してそのくらいは十分に持ちますね!!
面布団の肩の当たる部分とかフチなどはどうしても「摩擦」が激しいため傷んでしまいますのでそういった箇所は紺革を当てたり紺の布を当てたりして修理していきます。
また、痛みの激しいのはやはり「小手」の手の内です。この手の内は鹿革を使用していたり、人工皮革やクラリーノなど使用していますが、竹刀を握る為「穴」が開いたりまた、穴の小さいうちに修理すればよいのですが大きくなってからだと「鹿革」または「クラリーノ」素材で張り替えなくてはならなくなる場合もあります。
小手の説明の部分でも案内しましたが、どうしても稽古が混んでくる(中学生や高校生、大学生」や剣道を専門でやっている特練の方などは毎日の稽古でまた稽古時間も長いことから小手の傷みは激しいものがあります。原因としてこたの汗が乾かない内に使用してしまうことが考えられます。稽古用の「替え小手」を用意して交互に使用していきますと痛みも少なくまた、修理り出しても困りませんね。
胴は固い素材でできていますので面や小手に比べて痛みも少ないですが胴の下のヘリの所が垂と擦れて摩耗してしまうこともあります。この場合はヘリの交換修理が可能です。
垂は垂紐の摩耗が考えられますがかなり使用してからの修理になると思います。この紐の修理は紐の取り換え修理でカバーできます。
あと考えられる修理は、垂のヘリの部分が摩耗捨てきますので傷んだ部分に紺革など当てた修理になります。
小手以外かなり長い年月がしてからの修理になると思います。高価なミシン刺し防具や手刺し防具は素材も良いものを使用していますので長い方は30年や40年にわたって使用している方が多いですね。
細目なお手入れと傷んだ所のチェックを欠かさずまた、直射日光を避け風通しの良い所で保管し、可能な限り乾いてからの仕様を心掛けると何年も長く使用できますね。
防具っていつ頃からの物なのでしょう?
多くの書に防具の原型は江戸時代の中期(17世紀半ば)頃から直心影流剣術などで存在するようになり現在に近い防具の形は江戸時代後期になってからと言われていますね。
鎧や兜を基として携帯性や着装時の動きやすさなどを考えて形状や軽さや丈夫さ、衝撃の吸収度合いなど素材などの研究を重ねて現在の防具の作りへと変化していったものです。
その昔は着物姿に木刀の形状をした木剣を手に稽古をしたものと思われますが怪我も絶えられなかったと想像できます。
防具の進化に伴い現在の「竹刀」竹を四つに割った竹刀が考案され打突の際の衝撃など軽減されてきました。そういったことから、木刀は日本剣道型、木刀による剣道基本型稽古法などの形稽古に変わり、竹刀は試合形式の打ち込み稽古に代わってきました。
昔の試合は最初に相手の面を脱がせた方が勝ちとしていたと聞いています。
江戸時代には「武具」とか「道具」「武足」などの名称で呼ばれていたようです。
当時の「武具」今で言う「防具」は布の中に綿を入れてそれを手で縫い中の綿が動かないように固定して作られたように思われます。(私の感覚で)ですので全て手で作られていたものですね。今で言う2分刺しの手刺しのように大きく刺してあるのがその名残でしょうか?
余談ですが私は3分刺しの防具を使用しています。通常の防具に比べ「厚い」ですが面や小手を打たれても「痛くありません」安心して元立ちができます。
また、胴に関してですが、古い防具を見ますと少年用の防具も「竹」で出来ていてその上に「に皮」を張り付けた胴であったわけです。現在の胴はその上に漆を塗り高価な胴に仕上げているわけです。
現在は少年用や中学生用など少し安い価格で売られている防具の胴はヤマト胴など樹脂で作られていますね。
剣道は何故練習のことを「稽古」と言い、稽古する場所を他のスポーツと違い何故「道場」と呼ばれたりしているのでしょうか?
剣道は昔から仏教と深い関係があると考えられています。剣道修行の目的に「剣の理法の修練による人間形成の道である」と定義されています。
人間形成の道とは、前回の「手拭」のブログの中でも説明していますので詳しくは底を見ていただければありがたいのですが、「仁義礼智信」ではないかと思います。
僧侶が弟子に説法する場所が本堂とは別棟に建てられた屋敷つまり「道場」と呼ばれるところで行われていたことから剣道を稽古する場所のことを体育館とかでなく「道場」とか中学校や大学などでは「剣道場」と飛ばれているものです。
市や県の施設でも剣道場と言われ体育館とは別に設けていますね。また道場には「神前」と言われ「神棚」が設けれれています。武道場は「神聖」な場所でもあります。
私たちが道場に入るとき「今日も良い稽古ができますように」と心を込めて頭を下げて道場に入ります。また稽古が終わった時も「怪我無く元気に稽古させていただきました、ありがとうございました。」と言う感謝の気持ちを込めて挨拶させていただき道場を後にします。(個人によって言葉の違いがあります。)
また、年に一度「奉納演武」と言い神社の神楽殿で1年間の自分の修行の成果を神様に見ていただく儀式もありますね。また、自分の修行している武術、例えば「杖道」「居合道」「古武道」などの元祖が祭られている神社などで「奉納演武」をすることもありますね。
剣道は強くなることも目的の一つでもありますが大事なことは「人間形成の道」人に信頼され、人に思いやりの持てる人間「仁義礼智信」の精神の修行ができればと思っています。

安い特価防具です。
6mm刺し・ヘリクラリーノ仕立て
面は軽いジュラルミン面金・布団は使用し易い斜め刺し
胴はヤマト胴台・ヘリは素敵な返しべり
小手は織刺し手の内茶クラリーノパンチ
垂は織刺の飾り付きヘリ革付き3段飾り

洗える”面”になります。
ジャージ生地で非常に軽くて暑い夏の稽古には最高です。
ホウワの取り外しが容易で簡単に選択ができます。
あの嫌な”汗のニオイ”を感じたらサツっと外してジャブジャブと洗います。
ホウワが1ケ付いていますので乾くまでは変えホウワを使用してください。
何時でも爽やかに気持ちよく稽古に励めます!!
う